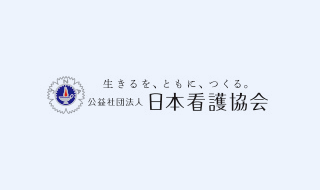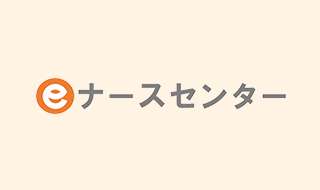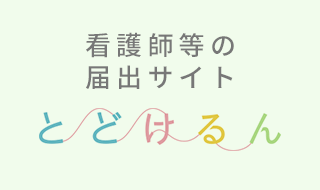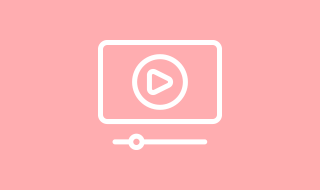令和7年度 重点事業

重点事業の概要
わが国では、少子超高齢社会の人口及び疾病構造を見据えた社会保障制度改革、特に地域包括ケアシステムの構築、医師の働き方改革などの医療提供体制の再構築に向けた取り組みや、少子化対策・子ども政策の強化、女性・高齢者の労働参加が進められている。
さらに、団塊ジュニアが高齢者となる一方で支える人口が減少するなどの様々な社会情勢の大きな変化が見込まれる2040年に向け、一層の制度や体制の整備が求められており、県において「県民一人ひとりが、健やかに地域で暮らし、心豊かに長寿を全うできる総合的な保健医療福祉システムづくり」を基本理念とした第8次医療計画が策定された。
このような状況の中、全国的な課題である看護職不足は継続しており、本県の従事者数は令和4年末現在62,016人で人口10万人当たりの職員数は全国45位と低い水準にあり、看護職の定着・確保対策は重要課題である。病院や訪問看護ステーションに勤務する看護職の離職率は高止まりの傾向にあり、労働環境・処遇改善など働き続けられる環境づくりの推進に取り組むとともに、次世代を担う人材の確保やプラチナナースの活躍推進がますます重要になっている。
令和5年10月に改正された「看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」には、量的確保と資質向上を図りながら看護職の確保を推進する方向性が示された。
県民の健康上のニーズの増大や、デジタル改革等の社会の変化に対応し、看護職が役割を発揮するためには、新たな知識や技術を学び直すため看護職自身が生涯学習に主体的に取り組み、自らキャリア形成に努めること、職能団体や所属する組織には生涯学習を支援する役割が求められている。
さらに、県民に質の高い看護を提供するためには、専門・認定看護師、認定看護管理者、特定行為研修修了者等の活躍促進に向けた取組みが重要である。
また、少子超高齢社会に向けて、医療は病院完結型から地域完結型への移行が加速しており、出生前から人生の最終段階に至る全世代を対象に、施設や地域等あらゆる場所で健康の保持増進から看取りまでを専門職や地域住民、自治体等が協働して支える共生社会のしくみである「全世代を対象とした地域包括ケアシステム」の構築・推進が必要である。加えて、近年の広範囲にわたる災害や新興感染症など県民の生命と生活を脅かす健康危機に対応する体制強化も重要である。
看護職の機能と役割を十分に発揮するため、千葉県、市町村と連携した政策策定への参画と看護政策の推進が重要となる。職能団体として、看護職に関わる様々な課題の解決を進め、地域の各実践の場において、看護職が的確に役割を果たすためには、医療・看護に係る政策の推進役となる本協会が、戦略的・継続的に看護政策を推進する力をつけていくことが必要となっている。そのためには、入会促進活動の推進により会員数を維持するとともに、職能間の連携強化が重要である。
以上により、令和7年度本協会は、社会の動向を見据え、看護職が果たすべき役割を見極めながら、看護の専門性を発揮し、県民の健康な生活を支えるべく、令和6年度に取り組んできた5つの重点事業を充実し、「地域における看護職の定着・確保の推進」「質の高い看護の提供体制の構築・推進」「全世代の健康を支える地域包括ケアの推進」「地域における健康危機管理体制の強化」「組織基盤の強化」とし、事業を展開する。
1 地域における看護職の定着・確保の推進
1-1 第5次看護職定着・確保推進計画の推進、評価
1-2 健康で安全な職場づくりの推進
1-3 安定的な定着・確保対策の実践(ナースセンター事業)
1-4 看護職の魅力の発信による次世代を担う人材の確保
2 質の高い看護の提供体制の構築・推進
2-1 生涯学習支援
2-2 看護研究学会の充実
2-3 認定看護師・専門看護師・認定看護管理者の活動推進に向けた啓発
2-4 特定行為研修制度の普及・活用
2-5 医療安全対策の推進
3 全世代の健康を支える地域包括ケアの推進
3-1 全世代を対象とした看護提供体制の強化
3-2 訪問看護の推進
4 地域における健康危機管理体制の強化
4-1 災害発生時の対応体制の整備
4-2 新興感染症等パンデミックへの対応体制の整備
5 組織基盤の強化
5-1 会員の定着・確保
5-2 看護政策推進力の強化

 施設用
施設用